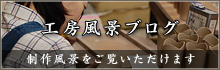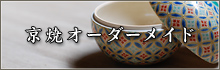太平洋高気圧が張り出してきているようです。少し落ち着いたお天気が続く様ですね。工房に朝から清々しい風が流れています。台風以後山間はすっかり秋色になってしまいました。飼っている犬たちも食欲が出てきたようで、何となく超えてきたように思います。まだまだこれからなのでしょうが、食欲の秋到来のようです。
各地で早場米が出始めています。新米の美味しい季節になりました。工房は新しい飯碗をHPに出していきます。使って楽しい、またご飯がおいしい飯碗。飯碗ができれば一人前とよく言われました。若い頃は「飯碗ぐらい、」と思っていましたが、陶芸を始め5年、10年とたってくると、何とも奥の深いものだと思うようになってきました。自分なりのオリジナルな飯碗となると、さあ、どうでしょうか。一生にどのくらいのものが出来るでしょうか。毎日使っても飽きのこない、それでいて益々愛着の湧く飯碗となると、そう簡単にできる物ではありません。
 さて、日本人はいつ頃から陶磁器を使ってご飯を食べだしたのでしょうか? 階級にもよりますが、町民あたりが使いだしたのはやはり江戸中期、伊万里で磁器が焼け、大量生産が可能になってからだと思われます。最初は上級クラスの高値の花だったものが、徐々に庶民にも使えるようになった。また、庶民が玄米から白米に変わっていいたのも、この時期だったと思います。日本人は長く木器で玄米を食していました。磁器の飯碗で白米を食べる。時代が大きく進歩したように思いますね。今と変わらない食卓の風景です。
さて、日本人はいつ頃から陶磁器を使ってご飯を食べだしたのでしょうか? 階級にもよりますが、町民あたりが使いだしたのはやはり江戸中期、伊万里で磁器が焼け、大量生産が可能になってからだと思われます。最初は上級クラスの高値の花だったものが、徐々に庶民にも使えるようになった。また、庶民が玄米から白米に変わっていいたのも、この時期だったと思います。日本人は長く木器で玄米を食していました。磁器の飯碗で白米を食べる。時代が大きく進歩したように思いますね。今と変わらない食卓の風景です。
そんなことを考えると、文禄、慶長の役は後々の日本に産業や経済を大きく推進させることになったと思います。近代の基礎を作る、意味深いものだったと考えられます。このことはもう少し時間を費やし深く書いてみたいと思っていますが、今食卓にある一つの飯碗から色々なことを考えられ、面白くなってきます。
日本人はお箸やお茶碗など自分自身のものを持って暮らしています。これも世界では珍しいことの一つだと思います。マイ茶碗、マイカップ、マイお箸などなど。生涯にいくつもの飯碗と出会い使い、ともに人生を生き抜いていく。飯碗、されど飯碗。そのような事を思いながら、今日も轆轤を回しましょう。がんばろ。















 近畿地方は大型の台風12号の影響で各地に大雨洪水注意報が出ています。ここ泉州地方にも朝から注意報が出ているのです。今、四国に上陸したとニュースが出ています。速度が遅いので一昨日からの雨量はかなりのものでしょう。幸い工房は平常通りです。
近畿地方は大型の台風12号の影響で各地に大雨洪水注意報が出ています。ここ泉州地方にも朝から注意報が出ているのです。今、四国に上陸したとニュースが出ています。速度が遅いので一昨日からの雨量はかなりのものでしょう。幸い工房は平常通りです。


 口作りの薄さ厚さや、手に持った時の重さ軽さ、焼き込みの違いなど、チェック項目は上げるときりがないですね。
口作りの薄さ厚さや、手に持った時の重さ軽さ、焼き込みの違いなど、チェック項目は上げるときりがないですね。


 お早うございます。昨日から窯を焚いています。乾山陶器を始めて三年になり、いろいろな物を創ってきました。この窯にも細工物が多く入っています。汁次の形をそのままに小型にして醤油差し。手付きの銚子、などなど。7月、8月はこの細工物を作るのに費やされてしまいました。かなりの手間仕事になってしまいました。しかし以前作った品物より一段と良くなったように思えます。何事も経験です。経験なくして進歩なし、ですね。
お早うございます。昨日から窯を焚いています。乾山陶器を始めて三年になり、いろいろな物を創ってきました。この窯にも細工物が多く入っています。汁次の形をそのままに小型にして醤油差し。手付きの銚子、などなど。7月、8月はこの細工物を作るのに費やされてしまいました。かなりの手間仕事になってしまいました。しかし以前作った品物より一段と良くなったように思えます。何事も経験です。経験なくして進歩なし、ですね。




















 お早うございます。8月も20日を過ぎるとすっかり季節が変わり、蝉の声もミンミン蝉やツクツク法師に変わってきました。昨日、日本ミツバチの師匠がやってきて、今年は20リットル、30リットルも採れたといっていました。さっそく我が家の巣箱も採蜜しようということで、ネットを被り慎重に巣箱を開けてみましたが、これもなかなか難しいものですね。お盆過ぎに採ろうと言っていたのですが、どうも時期を外したようで、分蜂した後だったようです。そういえば一週間程前巣箱にたくさんの蜂が飛んでいました。分蜂しているのかな?と思ったのですが、こちらも忙しくしていたので、お盆が終わったのに延ばし、延ばしした結果だと思います。非常に残念です。スムシは入っていなくて助かったのですが、師匠はこれからまだ蜜をとってくるから、岸和田祭りあたりにもう一度見てみよう、と慰めていました。今年こそと張り切っていたのですが、まあ、一縷の望みを託して観察していきます。
お早うございます。8月も20日を過ぎるとすっかり季節が変わり、蝉の声もミンミン蝉やツクツク法師に変わってきました。昨日、日本ミツバチの師匠がやってきて、今年は20リットル、30リットルも採れたといっていました。さっそく我が家の巣箱も採蜜しようということで、ネットを被り慎重に巣箱を開けてみましたが、これもなかなか難しいものですね。お盆過ぎに採ろうと言っていたのですが、どうも時期を外したようで、分蜂した後だったようです。そういえば一週間程前巣箱にたくさんの蜂が飛んでいました。分蜂しているのかな?と思ったのですが、こちらも忙しくしていたので、お盆が終わったのに延ばし、延ばしした結果だと思います。非常に残念です。スムシは入っていなくて助かったのですが、師匠はこれからまだ蜜をとってくるから、岸和田祭りあたりにもう一度見てみよう、と慰めていました。今年こそと張り切っていたのですが、まあ、一縷の望みを託して観察していきます。